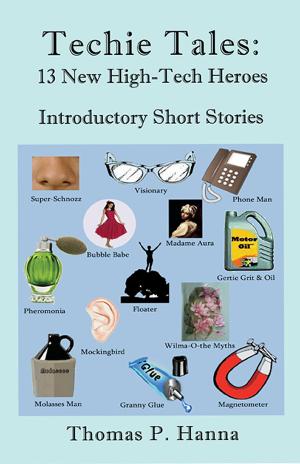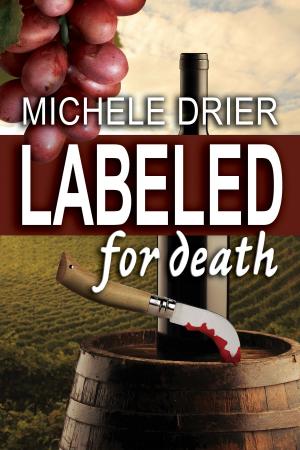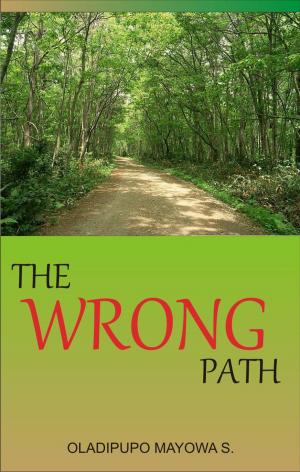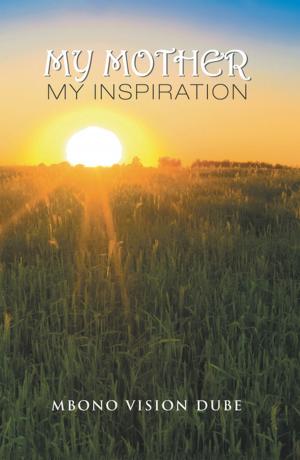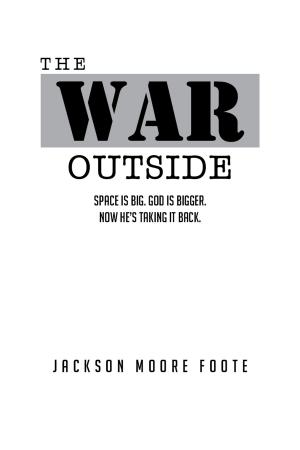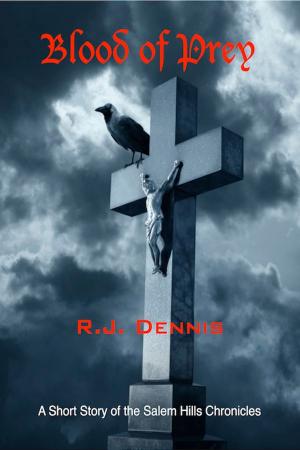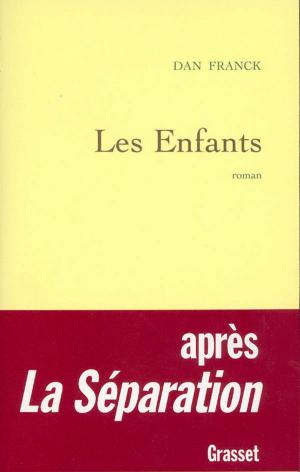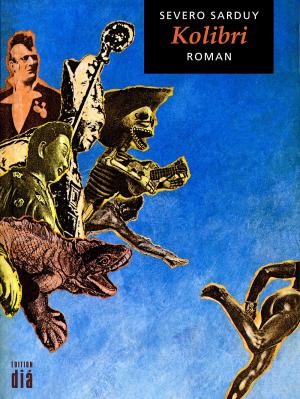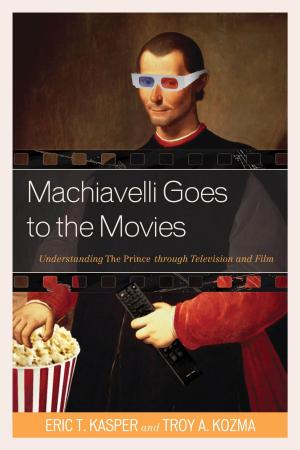TADACA
Nonfiction, Social & Cultural Studies, True Crime, Espionage, Religion & Spirituality, Philosophy, Fiction & Literature| Author: | 千慶烏子 | ISBN: | 9784908810183 |
| Publisher: | P.P.Content Corp. | Publication: | October 14, 2001 |
| Imprint: | Language: | Japanese |
| Author: | 千慶烏子 |
| ISBN: | 9784908810183 |
| Publisher: | P.P.Content Corp. |
| Publication: | October 14, 2001 |
| Imprint: | |
| Language: | Japanese |
人類の歴史にはじめてインターネットが登場したときに、人はどのような未来をそこに見いだし、詩人はどのような書物をそこに創造したのか──。
本書はSWFフラッシュ形式のデジタル作品として2001年に初版が出版された。わが国で最初かどうかは断定できないが、デジタルで書物を出版するという企ての最も初期に位置するものであることだけは間違いない。以来2003年、2007年、2011年と本書は版を重ねている。これはよく売れるから版を重ねているのではなく、伝統的な出版文化に慣れ親しんだ文学者が、デジタルと遭遇したときに、これをどう受け止め、そして作品の中でいかにデジタルを内面化し、またいかにしてそれをデジタルで表現するかに費やされた文学的営為の記録である。今回の電子書籍版を含めると、千慶烏子は、都合五回におよぶ出版と二十年の歳月を本書に費やしている。
先駆者の営為はそういうものなのかもしれないが、必ずしも正当に評価され、必ずしも正当に次代に受け継がれるものであるとは限らない。むしろそれは忘れられ、忘却の淵に沈み、長い年月を費やした後にあらためて発掘されるものであるのかもしれない。本書『TADACA』も発掘の時を待って忘却の淵に沈んでいると言っていい。千慶烏子が完成に十数年費やした本書オリジナル版は、映像と音響とテクストの融合したマルチメディア的なデジタル作品として制作された。その先進性と高度な芸術的達成に対し、当時は国内よりもむしろ海外から熱い賞賛が贈られたものであると聞く。制作に十数年を費やしたというだけあって作品の完成度は高く、映画『ラ・ジュテ』を思わせるモノクロームの映像と海辺の環境音が交差する本書オリジナル版は、まさしく「読む映画」と呼ぶにふさわしい段階に達している。おそらく詩人は、この映像・音響・言葉の重層する空間にデジタル化された書物の来るべき未来を見たのではないだろうか。
しかし、デジタル黎明期の詩人が見た夢は、テクノロジーの進化によって、容易く覆されることになる。携帯型デバイスの登場とその爆発的な普及により、千慶が情熱を傾けたSWF形式のフラッシュは廃れ、エディトリアル・デザインもまた、美的に洗練されたソリッドなレイアウトからマルチデバイス対応のリフロー型のデザインが主流になる。書物をめぐる洗練された美的な企て、あるいは芸術家の野心的な企ては、電子出版にとって無用の長物となる。2010年になると、電子書籍の国際的な標準規格が策定され、規格の統一が進む一方、書籍コードのデジタル適用のガイドラインが提案され、誰でも本を出版することができるという謳い文句のもとで、デジタル出版は画一的になり、平準化する。実験的で先鋭的な性格は失われ、大衆的で商業的な性格が強くなる。しかし、これはテクノロジーが普及し、広範な支持を獲得してゆく中で辿らざるを得ない一連の過程であるにちがいない。おそらく今日の読者の皆さんからするならば、千慶烏子のデジタル出版は、都市と都市とを結ぶ航空路が発達するはるか昔、大空に限りない夢とロマンを見たライト兄弟の絶えざる不可能への挑戦を思い浮かべていただくといいのではないだろうか。
この絶えざる不可能への挑戦のなかで、千慶烏子は、デジタルの登場という歴史的現象を哲学的な問いかけとして受け止め、これを内面化してゆくことになる。本書は、しばしば難解と言われる千慶の書物の中でも特に難解な作品である。この解説では、しばしその難解さに分け入って本書を簡単に概観してみたい。
本書『TADACA』は四章からなり、それぞれテクスト論・書物論・写真論・欲望論の「批評」を横糸に、二人の男女の不可能な愛の行程を描く「詩編」を縦糸に、作品は織り成されている。読者は交互に配された批評と詩編を読むことで、縦横に織り上げられたテクストの襞、文彩、織り込まれた模様を読み解いてゆくことになる。平易な作品を読み慣れた読者には、この構成は難しく映るかもしれない。だが、難解さに直面して辟易するよりも、詩編と批評の間を、テクストの織り目を、織り上げられたテクストの襞を辿りながら、デジタル黎明期の詩人が見た光景にひと時たゆたってみるのはいかがだろうか。それはわれわれの今日に直結する過去であり、過去の中に眠っている未来であり、未来において発現するであろう過去であり、これを紐解いてみることはわれわれの今日をより有意義なものにしてくれるにちがいない。
特に第三章「La Chambre Numerique」における写真論は傑出している。千慶烏子は、カメラのデジタル化によって過去のものとなる銀塩写真を取り上げ、この失われゆくテクノロジーから「物質的な感受性」をはじめとする非常に有効な概念を次々と拾い起こしてくる。そして、暗い部屋に横たわる「感じやすい物質」(これは写真装置におけるフィルムの暗喩であるが、それ以上に、人間というものを捉える新しい切り口である)がデジタルという空間に横断されてゆくさまを通して、デジタルというテクノロジーの内面化を行ってゆくのである。その思考を構成する概念の一つ一つが削り出しであり、ハンドメイドであり、千慶烏子のオリジナルである。先ほどのライト兄弟の喩えを続けるならば、飛行機を構成するプロペラ、高度計、筐体といったパーツからそれを留めるネジの一つ一つにいたるまで、千慶烏子は独力で作り出しているのである。現代思想に精通した千慶は、英語・フランス語を駆使して、彼の削り出しの思考をより普遍的なものにしようとしていることにも注意を促しておきたい。ここにもまた読者の皆さんは、忘れられた未来、あるいは過去の中に取り残された未来を見つけ出すことができるにちがいない。
このデジタルの内面化の過程を通して、実に驚くべきことだが、デジタルは人間的なものになる。もちろん数で構成されたデータが人間化するわけではない。絶えざる人間的な営みの積み重ねの中で、デジタルの登場もまた人間的な営為の一つとして人類の歴史に新しいページを刻んでゆくのである。内面化は人間化であり、そしてまた歴史化である。千慶烏子が本書で行っている思考の企ては、テクノロジーの進化と変遷を、人間的なエピステモロジーの領域の中に位置づけ、これを歴史的に捉えようとするものである。ライト兄弟の喩えで言うならば、空を飛ぶテクノロジーを航空力学や航空工学のもとで思考するのではなく、人間が空を飛ぶということが、いかに人類の世界観に大きな影響を及ぼし、人間の物の考え方や認識の体系に大きな変化をもたらしたのか、ちょうどこれらに比肩するような事がらを、千慶烏子はデジタルという問題に即して行っているのである。この一連の企てを通して(その絶えざる不可能な挑戦、そしてまたその極めて思索的な内面化の過程を通して)、デジタルというテクノロジーは歴史的人間性のもとで語られうるものになる。
「新しいわたしたちの「数の部屋」のなかでは、書かれたものの身体は、印刷されたものの物質性においてみずからを見いだすのではなく、複製されるものの感受性においてみずからのありようを見いだす。感じやすさとは、他なるものに横切られてある身体のはかないありようの謂いであるが、またそこにむけてあふれてゆく身体のゆたかさでもある。感じやすさとは、横切られてあるもののゆたかさである。」(本書第三章「La Chambre Numerique」より)
デジタルかフィジカルか、デジタルかアナログかといった問題の捉え方がいかに一面的であり、皮相的なものであるかに読者の皆さんは気づかれるにちがいない。千慶烏子のデジタル出版の企ては、書物というものの絶えざる積み重ねの中にデジタル化された書物を基礎づけ、また自らのデジタル出版された書物の中に、書物という人類の英知の普遍性を見いだそうとするものにほかならない。これが今から二十年も昔、インターネットが登場してまだ間もない頃に、日本語で書き記されたことに、読者の皆さんは驚きを禁じえないだろう。
千慶烏子の二十年に及ぶ行程が決して一様なものでなかったであろうことは想像に難くない。だが、無知と偏見に囚われた旧弊な人びとのことは論わないでおこう。ただ、この未知のものに対する絶えざる不可能な挑戦を通じて、あるいは前人未踏の単独者の行程を通して、千慶烏子のエクリチュールはより強靱さを増し、その表現はより深みと繊細さを増したであろうことだけは間違いない。時代を超えてゆく力、時代を超えて歴史を証言しようとする文学者の使命を果たすに足る力を千慶烏子が備えてくるのは、本書以降のことである。その圧倒的なまでに孤立無援の旅の始まりに位置するものとして、本書をご覧いただくのもいいかもしれない。
最後になったが、本書の表題『TADACA』はフランスの思想家ロラン・バルトの写真論『La Chambre Claire(邦題「明るい部屋」)』の一節から取られたものである。千慶烏子はこの短いフランス語を翻訳するにあたって、「ほら、ここに、このようにして」と大胆な意訳を試みている。それが何であれ、紙の本であれ、デジタル化された書籍であれ、ほら、ここに、このようにして、書物が存在するということは、何と偉大な人類の英知の賜物ではないだろうか。(P.P.Content Corp. 編集部)
人類の歴史にはじめてインターネットが登場したときに、人はどのような未来をそこに見いだし、詩人はどのような書物をそこに創造したのか──。
本書はSWFフラッシュ形式のデジタル作品として2001年に初版が出版された。わが国で最初かどうかは断定できないが、デジタルで書物を出版するという企ての最も初期に位置するものであることだけは間違いない。以来2003年、2007年、2011年と本書は版を重ねている。これはよく売れるから版を重ねているのではなく、伝統的な出版文化に慣れ親しんだ文学者が、デジタルと遭遇したときに、これをどう受け止め、そして作品の中でいかにデジタルを内面化し、またいかにしてそれをデジタルで表現するかに費やされた文学的営為の記録である。今回の電子書籍版を含めると、千慶烏子は、都合五回におよぶ出版と二十年の歳月を本書に費やしている。
先駆者の営為はそういうものなのかもしれないが、必ずしも正当に評価され、必ずしも正当に次代に受け継がれるものであるとは限らない。むしろそれは忘れられ、忘却の淵に沈み、長い年月を費やした後にあらためて発掘されるものであるのかもしれない。本書『TADACA』も発掘の時を待って忘却の淵に沈んでいると言っていい。千慶烏子が完成に十数年費やした本書オリジナル版は、映像と音響とテクストの融合したマルチメディア的なデジタル作品として制作された。その先進性と高度な芸術的達成に対し、当時は国内よりもむしろ海外から熱い賞賛が贈られたものであると聞く。制作に十数年を費やしたというだけあって作品の完成度は高く、映画『ラ・ジュテ』を思わせるモノクロームの映像と海辺の環境音が交差する本書オリジナル版は、まさしく「読む映画」と呼ぶにふさわしい段階に達している。おそらく詩人は、この映像・音響・言葉の重層する空間にデジタル化された書物の来るべき未来を見たのではないだろうか。
しかし、デジタル黎明期の詩人が見た夢は、テクノロジーの進化によって、容易く覆されることになる。携帯型デバイスの登場とその爆発的な普及により、千慶が情熱を傾けたSWF形式のフラッシュは廃れ、エディトリアル・デザインもまた、美的に洗練されたソリッドなレイアウトからマルチデバイス対応のリフロー型のデザインが主流になる。書物をめぐる洗練された美的な企て、あるいは芸術家の野心的な企ては、電子出版にとって無用の長物となる。2010年になると、電子書籍の国際的な標準規格が策定され、規格の統一が進む一方、書籍コードのデジタル適用のガイドラインが提案され、誰でも本を出版することができるという謳い文句のもとで、デジタル出版は画一的になり、平準化する。実験的で先鋭的な性格は失われ、大衆的で商業的な性格が強くなる。しかし、これはテクノロジーが普及し、広範な支持を獲得してゆく中で辿らざるを得ない一連の過程であるにちがいない。おそらく今日の読者の皆さんからするならば、千慶烏子のデジタル出版は、都市と都市とを結ぶ航空路が発達するはるか昔、大空に限りない夢とロマンを見たライト兄弟の絶えざる不可能への挑戦を思い浮かべていただくといいのではないだろうか。
この絶えざる不可能への挑戦のなかで、千慶烏子は、デジタルの登場という歴史的現象を哲学的な問いかけとして受け止め、これを内面化してゆくことになる。本書は、しばしば難解と言われる千慶の書物の中でも特に難解な作品である。この解説では、しばしその難解さに分け入って本書を簡単に概観してみたい。
本書『TADACA』は四章からなり、それぞれテクスト論・書物論・写真論・欲望論の「批評」を横糸に、二人の男女の不可能な愛の行程を描く「詩編」を縦糸に、作品は織り成されている。読者は交互に配された批評と詩編を読むことで、縦横に織り上げられたテクストの襞、文彩、織り込まれた模様を読み解いてゆくことになる。平易な作品を読み慣れた読者には、この構成は難しく映るかもしれない。だが、難解さに直面して辟易するよりも、詩編と批評の間を、テクストの織り目を、織り上げられたテクストの襞を辿りながら、デジタル黎明期の詩人が見た光景にひと時たゆたってみるのはいかがだろうか。それはわれわれの今日に直結する過去であり、過去の中に眠っている未来であり、未来において発現するであろう過去であり、これを紐解いてみることはわれわれの今日をより有意義なものにしてくれるにちがいない。
特に第三章「La Chambre Numerique」における写真論は傑出している。千慶烏子は、カメラのデジタル化によって過去のものとなる銀塩写真を取り上げ、この失われゆくテクノロジーから「物質的な感受性」をはじめとする非常に有効な概念を次々と拾い起こしてくる。そして、暗い部屋に横たわる「感じやすい物質」(これは写真装置におけるフィルムの暗喩であるが、それ以上に、人間というものを捉える新しい切り口である)がデジタルという空間に横断されてゆくさまを通して、デジタルというテクノロジーの内面化を行ってゆくのである。その思考を構成する概念の一つ一つが削り出しであり、ハンドメイドであり、千慶烏子のオリジナルである。先ほどのライト兄弟の喩えを続けるならば、飛行機を構成するプロペラ、高度計、筐体といったパーツからそれを留めるネジの一つ一つにいたるまで、千慶烏子は独力で作り出しているのである。現代思想に精通した千慶は、英語・フランス語を駆使して、彼の削り出しの思考をより普遍的なものにしようとしていることにも注意を促しておきたい。ここにもまた読者の皆さんは、忘れられた未来、あるいは過去の中に取り残された未来を見つけ出すことができるにちがいない。
このデジタルの内面化の過程を通して、実に驚くべきことだが、デジタルは人間的なものになる。もちろん数で構成されたデータが人間化するわけではない。絶えざる人間的な営みの積み重ねの中で、デジタルの登場もまた人間的な営為の一つとして人類の歴史に新しいページを刻んでゆくのである。内面化は人間化であり、そしてまた歴史化である。千慶烏子が本書で行っている思考の企ては、テクノロジーの進化と変遷を、人間的なエピステモロジーの領域の中に位置づけ、これを歴史的に捉えようとするものである。ライト兄弟の喩えで言うならば、空を飛ぶテクノロジーを航空力学や航空工学のもとで思考するのではなく、人間が空を飛ぶということが、いかに人類の世界観に大きな影響を及ぼし、人間の物の考え方や認識の体系に大きな変化をもたらしたのか、ちょうどこれらに比肩するような事がらを、千慶烏子はデジタルという問題に即して行っているのである。この一連の企てを通して(その絶えざる不可能な挑戦、そしてまたその極めて思索的な内面化の過程を通して)、デジタルというテクノロジーは歴史的人間性のもとで語られうるものになる。
「新しいわたしたちの「数の部屋」のなかでは、書かれたものの身体は、印刷されたものの物質性においてみずからを見いだすのではなく、複製されるものの感受性においてみずからのありようを見いだす。感じやすさとは、他なるものに横切られてある身体のはかないありようの謂いであるが、またそこにむけてあふれてゆく身体のゆたかさでもある。感じやすさとは、横切られてあるもののゆたかさである。」(本書第三章「La Chambre Numerique」より)
デジタルかフィジカルか、デジタルかアナログかといった問題の捉え方がいかに一面的であり、皮相的なものであるかに読者の皆さんは気づかれるにちがいない。千慶烏子のデジタル出版の企ては、書物というものの絶えざる積み重ねの中にデジタル化された書物を基礎づけ、また自らのデジタル出版された書物の中に、書物という人類の英知の普遍性を見いだそうとするものにほかならない。これが今から二十年も昔、インターネットが登場してまだ間もない頃に、日本語で書き記されたことに、読者の皆さんは驚きを禁じえないだろう。
千慶烏子の二十年に及ぶ行程が決して一様なものでなかったであろうことは想像に難くない。だが、無知と偏見に囚われた旧弊な人びとのことは論わないでおこう。ただ、この未知のものに対する絶えざる不可能な挑戦を通じて、あるいは前人未踏の単独者の行程を通して、千慶烏子のエクリチュールはより強靱さを増し、その表現はより深みと繊細さを増したであろうことだけは間違いない。時代を超えてゆく力、時代を超えて歴史を証言しようとする文学者の使命を果たすに足る力を千慶烏子が備えてくるのは、本書以降のことである。その圧倒的なまでに孤立無援の旅の始まりに位置するものとして、本書をご覧いただくのもいいかもしれない。
最後になったが、本書の表題『TADACA』はフランスの思想家ロラン・バルトの写真論『La Chambre Claire(邦題「明るい部屋」)』の一節から取られたものである。千慶烏子はこの短いフランス語を翻訳するにあたって、「ほら、ここに、このようにして」と大胆な意訳を試みている。それが何であれ、紙の本であれ、デジタル化された書籍であれ、ほら、ここに、このようにして、書物が存在するということは、何と偉大な人類の英知の賜物ではないだろうか。(P.P.Content Corp. 編集部)